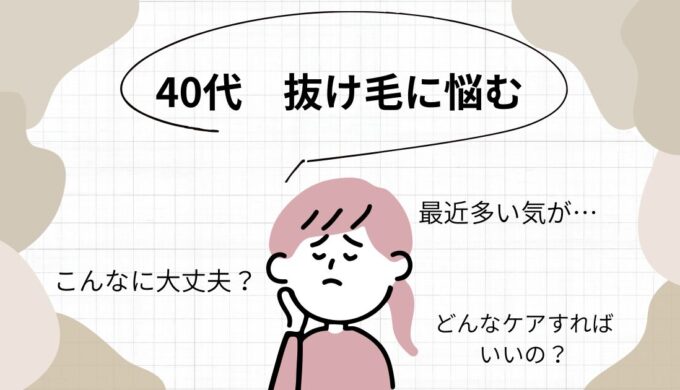こんにちは、ひいたです。
いやー、冷えてきましたね!
私の住んでるところは日本の北の方なので朝晩はだいぶ寒いです。あんなに布団を蹴飛ばしていた子供たちも、今は布団にくるまって寝ています。
冬に向かっていますが、皆さん体調はいかがですか?季節の変わり目や急に寒くなったことで体調崩されたりしていませんか?
私の周りでも体調不良者が見受けられます。私は寒くなってきたことで先月心が病んでました笑
今回は最近興味のある東洋医学の観点を交えて、冬に気をつけるべきことをご紹介します!
Contents
冬は何に気をつければいい?
東洋医学の観点から、冬は「閉蔵(へいぞう)」の季節、つまり、自然界のエネルギーが内に閉じこもり、蓄える時期とされています。人体もこれにならい、春に向けてエネルギーを温存し、次の活動期に備えることが大切です。特に、生命の根源的なエネルギーを蓄え、老化や免疫などにも関わる「腎(じん)」を養生することが重要視されます。
冬の養生における主な注意点は以下の通りです。

生活の養生:早寝遅起きと保温
冬は昼が短く夜が長いため、自然のリズムに合わせて早寝遅起きを心がけ、十分な休息をとってエネルギーの消耗を防ぎましょう。
・睡眠: 夜は早く寝て、朝は日が昇って暖かくなってから起きるのが良いとされます。
- 保温: 寒さから身体の陽気を守ることが最も重要です。
- 特に足首や腰回りなど、腎のツボがある部分を温め、冷気が入らないようにします。
- 暖房で部屋を暖かくしすぎると体表が開いて陽気が発散しやすくなるため、部屋の温度は控えめにし、衣服の工夫で暖かく保つのが良いでしょう。
- 活動: 激しい運動や発汗は体力を消耗し、陽気を発散させてしまうため控えめにします。軽いストレッチやウォーキングなど、適度に身体を動かす程度に留めましょう。
- 精神状態: 心身ともに活発になりすぎず、内向きに静かに過ごし、闘争心を抑えて平静な心構えでいることが、精神的な消耗を防ぐために大切です。
食事の養生:腎を補い、身体を温める
腎の働きを助け、身体を内側から温める食材を意識して摂取しましょう。
- 腎を養う食材:
- 東洋医学で腎に対応する色とされる黒い食材(黒豆、黒ごま、黒米、海藻類、きくらげなど)を積極的に摂ります。
- 鹹味(塩味)は腎の働きを助けますが、摂りすぎは禁物です。
- 身体を温める食材:寒い土地で採れるもの、冬が旬のもの、地中で育つ根菜類(ごぼう、にんじん、大根、かぼちゃなど)を摂ります。
- 調理法: 身体を冷やす生野菜などは避け、食材は茹でる、焼く、煮るなど、火を通して温かい状態で摂りましょう。
温めと血行促進
冷えを防ぎ、体内の「気」や「血」の巡りをスムーズに保つことも重要です。
- 入浴・足湯: 毎日のお風呂や足湯で体全体を温め、血行を良くしましょう。ぬるめ(38℃前後)のお湯にゆったりと浸かるのがおすすめです。
- マッサージ: 冷えやすい手足の末端を揉んだり、さすったりする簡単なマッサージは、末梢の血行を良くし、リラックス効果も期待できます。

腎って腎臓のこと?
東洋医学(漢方医学)でいう「腎(じん)」は、西洋医学の「腎臓」とは異なります。
東洋医学の「腎」は、解剖学的な臓器である腎臓の機能も含みますが、それ以上に広範囲な生命活動を司る機能のシステム全体を指しています。
東洋医学の「腎」の主な役割
東洋医学において、「腎」は「生命力の源」と考えられ、体の中でも非常に重要な役割を担っています。
- 「精(せい)」を蔵す(生命エネルギーの貯蔵庫)
- 生まれ持った生命力(先天の精)や、食事から得たエネルギー(後天の精)を蓄え、全身の活動の基礎となる生命エネルギーの源となります。
- 成長、発育、老化、生殖といった生涯にわたるプロセスを司ります。
- 水を主る(すいをつかさどる)
- 体内の水分の代謝や排泄を調整する機能です。これは西洋医学の腎臓の働きに比較的近いです。
- 骨を主り、髄を生ず(ずいをつくり、骨を支配する)
- 骨や歯の健康、骨髄(髄)、さらには脳や脊髄(これらも「髄」の一部とされる)の働きに関わります。
- 納気(のうき)を主る
- 呼吸時に取り込んだ「気」(エネルギー)を深く取り込み、全身に定着させる働きです。この機能が衰えると、息切れなどが起こりやすくなります。
- 華は髪にあり、竅は耳と二陰に開く
- 髪のツヤや生え方(華は髪にあり)や、耳の機能(聴覚)、尿道・肛門(二陰)の排泄機能と密接に関連しています。
ずっと腎臓のことかと思ってた…
腎の不調による体調不良例
腰痛
頻尿
耳鳴り
白髪
抜け毛
足腰のだるさ
性機能の衰え
これらは「腎」の不調(腎虚)とされています。
こうしてみると多岐に渡っていますね。「腎」を補うということがどれだけ大切か分かります。
まとめ
寒くなってくると腎の働きの低下により様々な不調を伴うことが分かりました。
冬って寒いし暗いしで気分まで沈み込む感じが嫌だったんです。でもそうゆう季節なんだって知れたことで気分が軽くなりました。
入浴等で外側から、食べ物で内側から身体を温めて静かに穏やかに冬を過ごしましょう。